1. 平安京エイリアンの歴史的背景
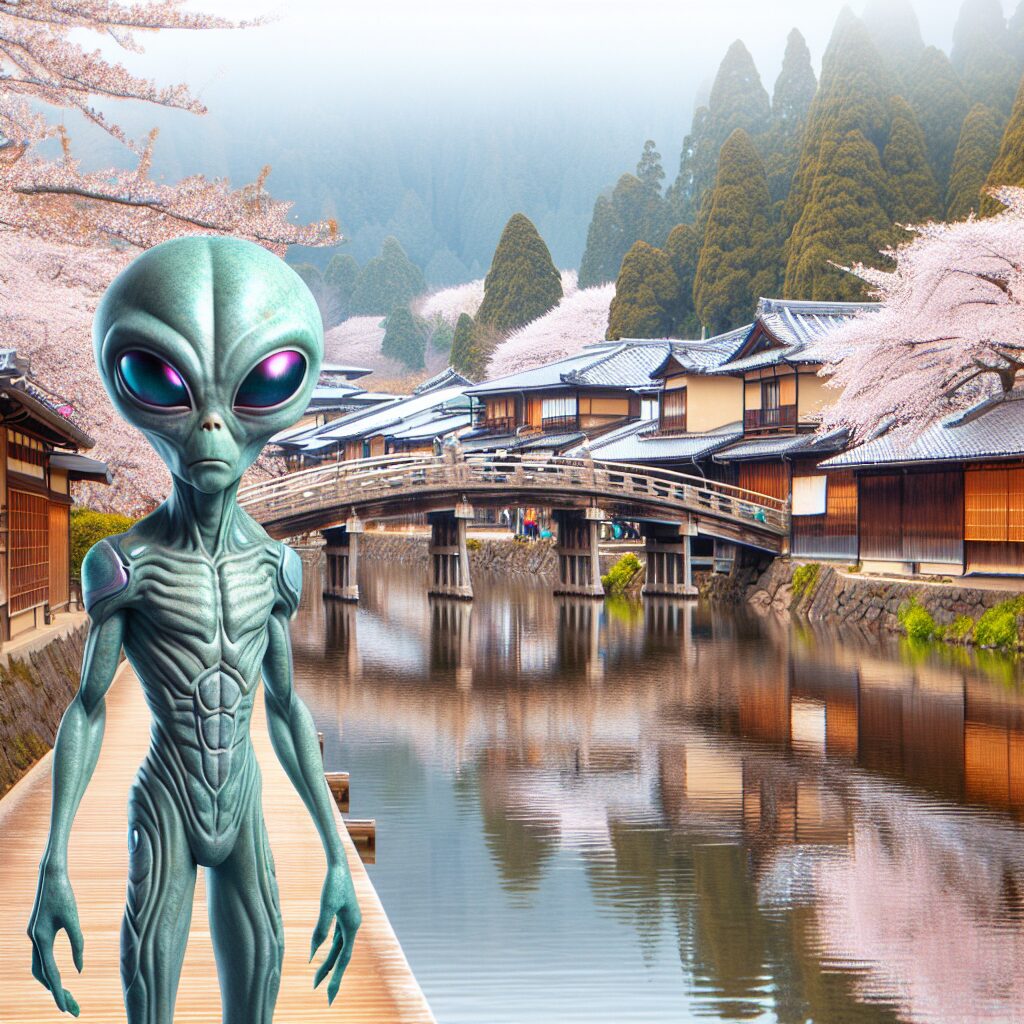
TSGとは、理論科学グループの略で、技術革新に努める集団でした。
Apple II版を皮切りに、TK-80BS、PC-8001、MZ-80Kなどのバージョンが続々と開発され、これらはその年の11月に開かれた駒場祭で初めて一般に公開されました。
この駒場祭での発表を契機に、平安京エイリアンは注目を集め、1980年には工学社の「I/O」でプログラムリストが紹介され、さらにカセット・サービスを通じた通信販売が開始されました。
この広がりに支えられ、そのゲームの価値は多くの人々に認知されていったのです。
一方、平安京エイリアンのアーケードゲームとしての展開も同時に進行していました。
1979年10月に行われたアミューズメントマシンショーで発表され、日本電気音響によって1980年1月から正式に稼働が始まりました。
アーケード版では、より広範なプレイヤー層にアプローチすることができ、ゲームの知名度はさらに高まりました。
ゲーム内容は、碁盤目状の通路上で検非違使を操作し、エイリアンを罠にかけて撃退するというものです。
検非違使は直接エイリアンを攻撃できず、「穴を掘る」ことでしか対抗できません。
このシンプルさが逆に戦略的な深みを生み出し、多くのプレイヤーを魅了しました。
また、東京大学が開発したという特異性も手伝い、メディアで度々取り上げられたことがその人気に拍車をかけました。
平安京エイリアンは、当時の大学生が限られた技術とリソースの中でどれだけ創造的かつ先進的なゲームを生み出せるかを示した好例となりました。
そして、これを機に生み出された創意工夫は、その後のゲーム開発にも大きな影響を与えることになったのです。
2. ゲーム内容の魅力
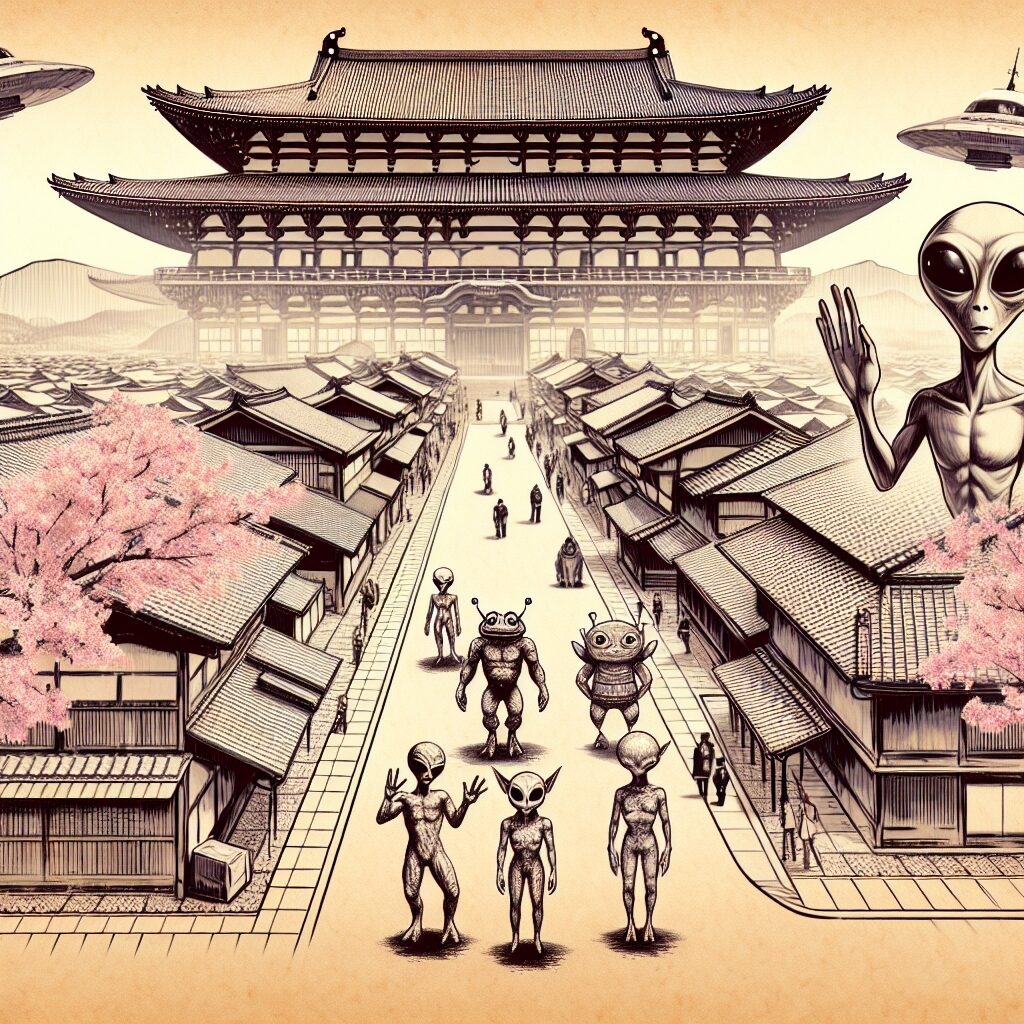
プレイヤーは、平安時代に想定される警察官的存在の検非違使となり、平安京に侵入してくるエイリアンを撃退します。ゲームのルールは非常にシンプルで、プレイヤーは穴を掘ってエイリアンをおびき寄せ、そこに落として埋めることで撃退するというものです。しかし、この単純なルールの中に、戦術的な駆け引きを楽しめる要素が詰まっています。例えば、敵を誘導して効率よく撃退するためには、どこに穴を掘るべきかを即座に判断しなければなりません。
ステージクリアの条件はすべてのエイリアンを撃退することにあります。通路は1マスの幅で構成されており、検非違使とエイリアンの動きはその限られた空間内に制限されています。そのため、限られたスペース内でどのように戦略を立てるかが勝敗の鍵となります。
また、このゲームはアーケードゲームとしても梶が進められ、日本では1980年にアミューズメントマシンショーで発表され、同年に電気音響によって稼働が開始されました。日本国内のみならず、海外でも数多く楽しまれ、そのシンプルさとゲーム性から多くのフォロワーを生み出しました。
『平安京エイリアン』はその後も多くのプラットフォームに移植され、特に大きな反響を呼んだことから、今なお一部のゲーマーから愛されています。この時代のゲームが持っていた創造性とその革新性は、現代のゲーム開発にも多大な影響を与えていると言えるでしょう。
3. 開発の裏側
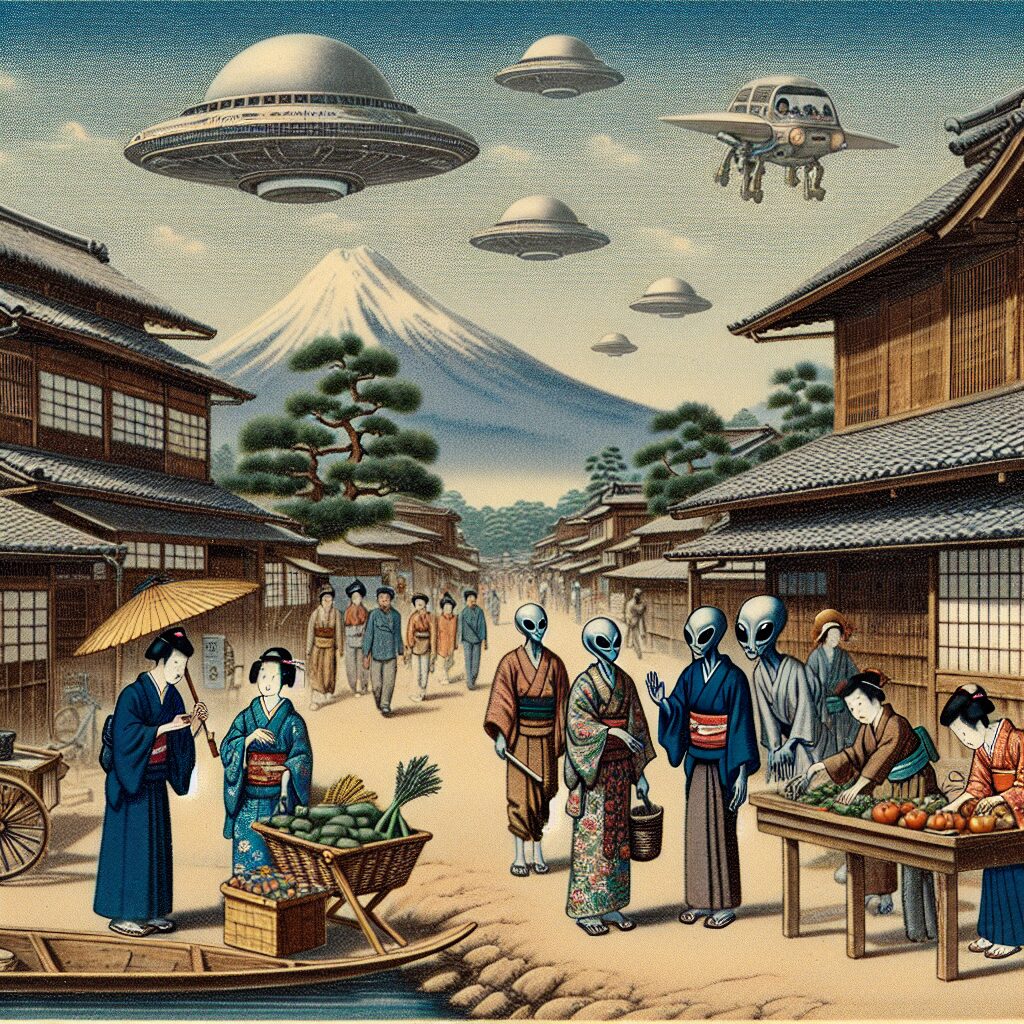
『平安京エイリアン』の開発は、たまたま東京工業大学が週刊朝日に取り上げられるという偶然の出来事が始まりでした。それをきっかけに東京大学への取材が持ちかけられ、そこでTSGは平安京エイリアンのアイデアを生み出すことになりました。通常の研究とは異なる、限られた時間の中での競争的なアイディア出しは、大学サークルならではのダイナミックな発想力を試される場でした。
TSGのメンバーは、そのアイディアを元にApple IIでのプログラム開発に着手しました。この時の開発環境や技術的な挑戦は、同時代の他の学生たちと共有され、大いに刺激し合う関係を築きました。このようにして開発された『平安京エイリアン』は、ナムコ、セガ、電気音響といった大手企業からも興味を持たれ、結果的に電気音響との協力に至ることとなりました。
4. メディアとアーケードでの反応

アーケードゲームとしての展開も興味深いものがありました。特に、ゲームのアーケード化に際しては、日本の電気音響の協力が不可欠でした。彼らの協力を得て、ゲームはよりプロフェッショナルな形でアーケード市場に投入され、多くのゲーマーたちを魅了しました。
1979年のアミューズメントマシンショーでは、その革新的なゲーム性から多くの注目を集めました。電気音響との協力により、プロフェッショナルな音響効果やグラフィックが実現され、アーケードでの体験を一層豊かにしました。こうした背景から、『平安京エイリアン』は単なるコンピュータゲームにとどまらず、社会的現象とも言える存在として、その名を歴史に刻むこととなったのです。
5. 最後に

このゲームは、まずApple II版として開発され、その後、TK-80BS版が作成され、さらにPC-8001版やMZ-80K版といった様々なプラットフォームで展開されました。
これらのバージョンは1979年11月に行われた駒場祭で初めて一般に公開され、かなりの話題を呼びました。
その中でも、特に注目を集めたのは、1980年2月に工学社の「I/O」誌にプログラムリストとして与えられたTK-80BS版です。
この版は同年4月から「I/O」の「カセット・サービス」を通じて通信販売が行われ、一般家庭でも楽しむことができるようになりました。
アーケード版も同様に注目されており、1979年10月にアミューズメントマシンショーで発表され、1980年1月にはすでに日本の電気音響によってアーケードゲームとして稼働し始めていました。
これにより、平安京エイリアンは固定画面ゲームのプレイヤーの間で急速に人気が広まりました。
その一方で、ゲームのルールはシンプルでありながら戦術的要素が取り入れられており、大変戦略的なゲームプレイが特徴です。
プレイヤーは検非違使を操作し、碁盤目状に配列された通路上でエイリアンを封じ込めます。
ゲームの操作方法は、まず「穴を掘る」ことでエイリアンを落とし込み、そのうえで「穴を埋める」ことで撃退するという極めてシンプルなものです。
しかし、この簡単な操作の裏には敵の動きを予測する戦略性が求められ、プレイヤーの計画性が試される内容となっています。
このような工夫が凝らされているため、発表当初から多くのプレイヤーの心を掴み、大変人気のゲームとなりました。
また、当時大学サークルがゲーム開発を手がけるという試み自体が先進的であり、注目を集めました。
平安京エイリアンが特に意義深いのは、東京大学の学生が主体となって開発を進めたという点です。
アイディア出しはサークル活動から始まり、後にTSGのメンバーがApple IIでのプログラム開発を担いました。
ナムコ、セガ、電気音響などの大手からも注目され、特に電気音響のバックアップでアーケードゲームとして製品化されました。
このように、学生たちの斬新な発想と実行力が見事に結実し、現在でも語り継がれるゲームとしてゲーム史に名を連ねているのです。
