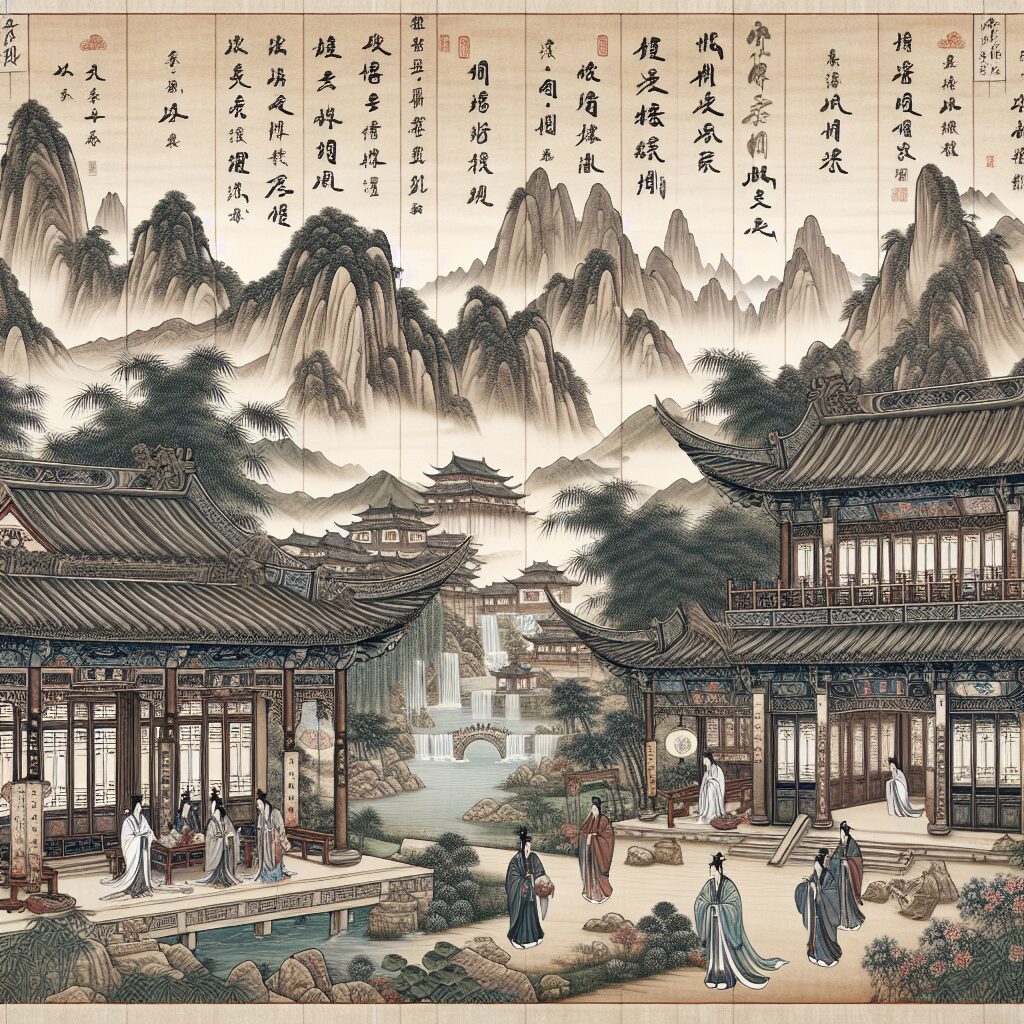1. ゲームの基本情報

『三國志III』は、1992年に日本の光栄からPC-9801向けに発売された歴史シミュレーションゲームです。この作品は、古代中国の壮大な歴史を舞台に、プレイヤーが複数の都市を制覇していくことが目的となっています。前作までは国全体の支配を目指すものでしたが、本作では都市の支配にフォーカスされ、戦略性が一層強化されています。本作では最大8人でのマルチプレイが可能であり、各プレイヤーは異なる君主を選択することができるのです。これにより、プレイヤー間の駆け引きと戦略がより楽しめるようになっています。また、『三國志III』はその後のゲーム機への移植も積極的に行われ、スーパーファミコンやメガドライブ、PlayStationといったさまざまな機種で楽しむことができました。
プロデューサーのシブサワ・コウの手腕により、ゲームの音楽はカシオペアの向谷実さんが担当し、前作『三國志II』と同様の音楽的世界観を保ちながらも、新たな要素を加えています。さらに、ニンテンドーDSや3DS用にも、この作品をベースにしたゲームが登場し、長い間愛され続けている名作です。
2. 都市支配という新たな勝利条件

ゲームの進化には常に新たな挑戦が付きまとうものですが、『三國志III』も例外ではありません。
前作までの「国の支配を目指す」勝利条件が、本作では「都市支配」へと進化を遂げたことで、プレイヤーに新たな戦略と挑戦が求められることになりました。
古代中国の全都市を支配することで、初めてゲームクリアとして認められるこのシステムは、プレイヤーの戦略性を一層高めています。
具体的には、都市ごとに異なる特性を理解し、それぞれに適した支配方法を考えなければ勝利は遠のくため、より深い分析と計画性が問われるようになっています。
この新システムは、古代中国の地理や政治的背景を理解しながらゲームを楽しむという、従来にはない魅力をプレイヤーに提供します。
また、この都市支配というコンセプトは、よりリアルな歴史シミュレーション体験を提供することに貢献しています。
都市ごとの違いをどのように攻略していくか、それがプレイヤーの自由な選択に委ねられている点も、見逃せないポイントです。
『三國志III』では、プレイヤーは全ての君主を選択可能で、各君主には異なる特性や戦略が求められるため、どの君主を選ぶかによってもプレイ体験が大きく異なってきます。
この多様性があるため、何度プレイしても新たな体験が得られる楽しさがあります。
前作までの「国の支配を目指す」勝利条件が、本作では「都市支配」へと進化を遂げたことで、プレイヤーに新たな戦略と挑戦が求められることになりました。
古代中国の全都市を支配することで、初めてゲームクリアとして認められるこのシステムは、プレイヤーの戦略性を一層高めています。
具体的には、都市ごとに異なる特性を理解し、それぞれに適した支配方法を考えなければ勝利は遠のくため、より深い分析と計画性が問われるようになっています。
この新システムは、古代中国の地理や政治的背景を理解しながらゲームを楽しむという、従来にはない魅力をプレイヤーに提供します。
また、この都市支配というコンセプトは、よりリアルな歴史シミュレーション体験を提供することに貢献しています。
都市ごとの違いをどのように攻略していくか、それがプレイヤーの自由な選択に委ねられている点も、見逃せないポイントです。
『三國志III』では、プレイヤーは全ての君主を選択可能で、各君主には異なる特性や戦略が求められるため、どの君主を選ぶかによってもプレイ体験が大きく異なってきます。
この多様性があるため、何度プレイしても新たな体験が得られる楽しさがあります。
3. 音楽と開発の背景
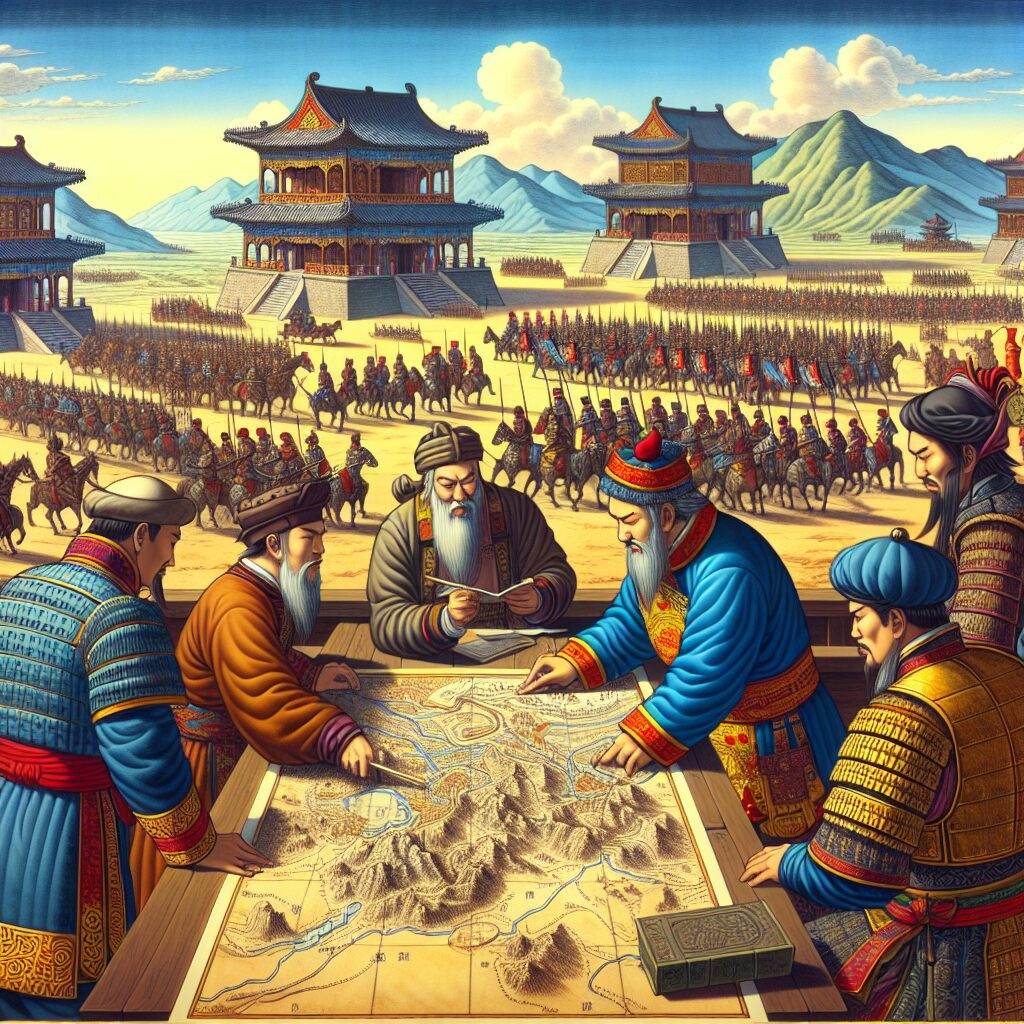
『三國志III』における音楽と開発背景は、その魅力をさらに引き立てる重要な要素です。開発は光栄が担当し、プロデューサーはシブサワ・コウさんという名前で知られる著名なゲームプロデューサーが指揮を執りました。彼のビジョンのもと、ゲームはよりリアルな戦略体験を提供するために綿密に設計されました。音楽面では、フュージョンバンド「カシオペア」のメンバーである向谷実さんが音楽を担当しました。彼の豊かな音楽の才能によって、『三國志III』はプレイヤーに強い印象を与えるサウンドトラックが特徴です。向谷さんの音楽は、ゲームの緊張感やドラマティックなシーンを一層引き立て、プレイヤーにより深い没入感を提供します。そのサウンドトラックの人気は高く、一つの作品としても評価されています。
このゲームが持つ音楽のこだわりは、単にバックグラウンドミュージックとしての役割を超えて、プレイヤーにとってのゲーム体験をより記憶に残るものにしています。音楽とゲームデザインの絶妙な融合が、『三國志III』の進化した魅力を形成しているのです。
4. 移植と北米版の展開
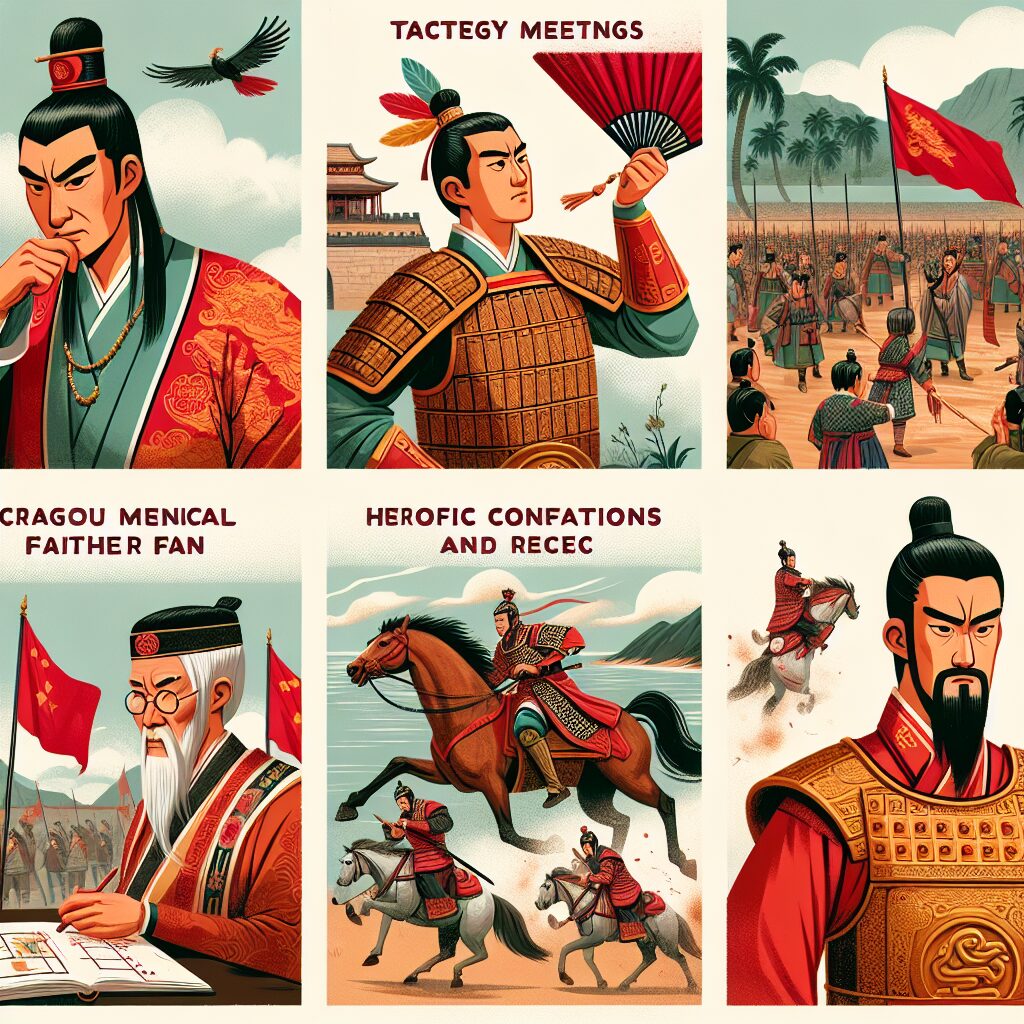
『三國志III』は、1992年に光栄(現・コーエーテクモゲームス)が日本で発売した歴史シミュレーションゲームで、PC-9801を対象に開発されました。
このゲームは、ユーザーに古代中国の都市を支配するという新たなゲームプレイの目的を提供し、大きな人気を集めました。
発売後、ゲームは多くの日本製パソコンはもちろん、スーパーファミコンやメガドライブ、メガCD、PCエンジン、PlayStationといった家庭用ゲーム機にも移植され、その普及を広げました。
これにより、多様なプラットフォームのユーザーに愛される作品となりました。
また、『三國志III』は1993年に北米でも『Romance of the Three Kingdoms III: Dragon of Destiny』のタイトルでリリースされました。
この移植に当たっては、各プラットフォームの特性に合わせた調整が行われ、現地のプレイヤーに対しても快適なゲーム体験を提供することを目指しました。
その結果、ゲームは海外でも多くのファンを獲得し、日本国外における『三國志』シリーズの知名度を一層高めることに成功しました。
移植と調整を重ねた展開により、『三國志III』は国内外で長く愛される名作となったのです。
このゲームは、ユーザーに古代中国の都市を支配するという新たなゲームプレイの目的を提供し、大きな人気を集めました。
発売後、ゲームは多くの日本製パソコンはもちろん、スーパーファミコンやメガドライブ、メガCD、PCエンジン、PlayStationといった家庭用ゲーム機にも移植され、その普及を広げました。
これにより、多様なプラットフォームのユーザーに愛される作品となりました。
また、『三國志III』は1993年に北米でも『Romance of the Three Kingdoms III: Dragon of Destiny』のタイトルでリリースされました。
この移植に当たっては、各プラットフォームの特性に合わせた調整が行われ、現地のプレイヤーに対しても快適なゲーム体験を提供することを目指しました。
その結果、ゲームは海外でも多くのファンを獲得し、日本国外における『三國志』シリーズの知名度を一層高めることに成功しました。
移植と調整を重ねた展開により、『三國志III』は国内外で長く愛される名作となったのです。
5. 総集編としての後続作品

『三國志III』は1992年に日本で初めて登場し、独自の歴史シミュレーション要素で多くのユーザーを魅了しました。時代とともにこのゲームも進化を遂げ、ニンテンドーDSや3DS向けにリリースされた作品では様々な追加要素を搭載して、幅広いユーザー層へのアプローチを可能にしました。この革新により『三國志III』はただのリメイクに留まらず、より多くのプレイヤーに古代中国の戦略と知恵を体験させることができました。新たなユーザー層へのアプローチは、ゲームデザインやインターフェースの改善といった進化だけにとどまらず、ゲームを通じて中国歴史の深みや複雑さを現代のユーザーに伝える重要な役割も果たしています。『三國志DS』や『三國志2(3DS版)』は、単なる移植ではなく、ゲームを通じた新たな学びと体験の場を提供しています。
総集編としての後続作品は、単に過去の作品を再現するだけでなく、歴史的意義とシリーズの発展性を表現する点で大きな意味を持ちます。そして、これらは常にプレイヤーの創造力を刺激し続け、多くの人々に支持され続けています。
最後に
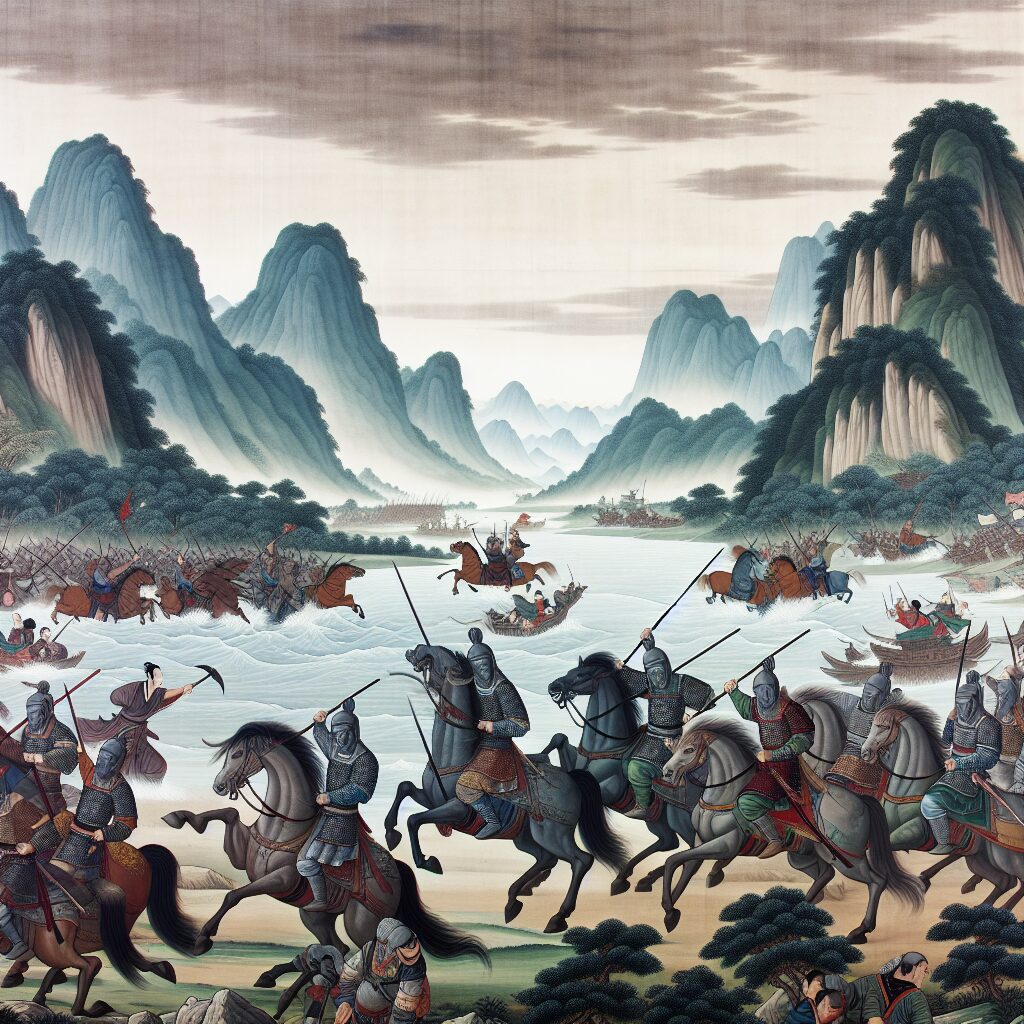
『三國志III』は、その革新的なゲームプレイにより歴史シミュレーションゲームのジャンルに新たな風を吹き込みました。1992年に光栄から発売され、都市の支配を目的とした新しいゲームデザインが特徴です。それまでのシリーズでは国家を支配することが主な目標でしたが、本作では古代中国の主要な都市をすべて支配することがゲームクリアの条件として設定され、この点が新鮮で多くのユーザーに支持されました。また、最大8人までのマルチプレイが可能となり、全ての君主を選べることができる仕様は、プレイヤーの自由度を格段に高めました。開発を担ったのは光栄で、プロデューサーはシブサワ・コウさんが務め、その音楽は前作に引き続き向谷実さんが担当しました。PC-9801版の発売後には、日本の多機種やスーパーファミコン、メガドライブ、PlayStationなどの家庭用ゲーム機、さらには北米版としてPC/AT互換機にも移植されています。このように多様なプラットフォームでプレイできることも、本作が長く愛される理由の一つです。
さらに、『三國志III』はその後のシリーズ展開にも影響を与えました。例えば、2006年のニンテンドーDS用『三國志DS』や、2015年のニンテンドー3DS用『三國志2(3DS版)』は、本作を基に製作されており、その進化の軌跡は現在でも多くのファンを魅了し続けています。